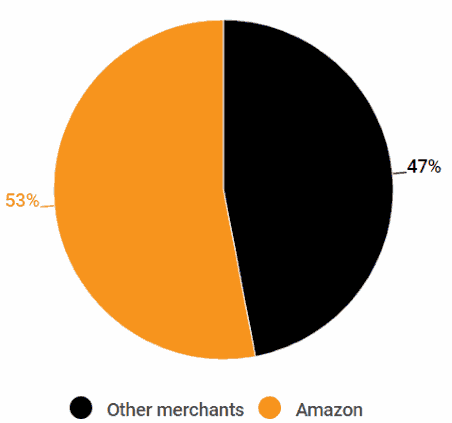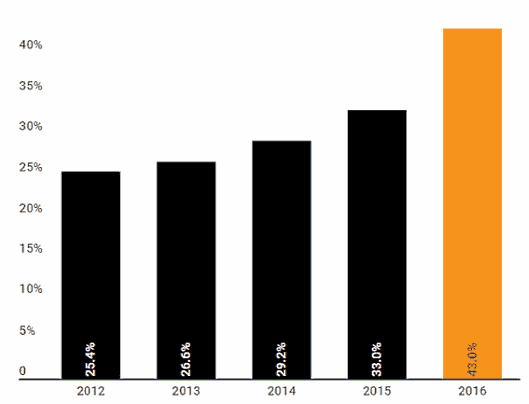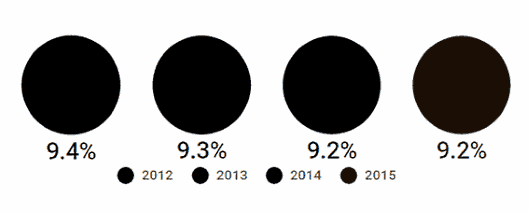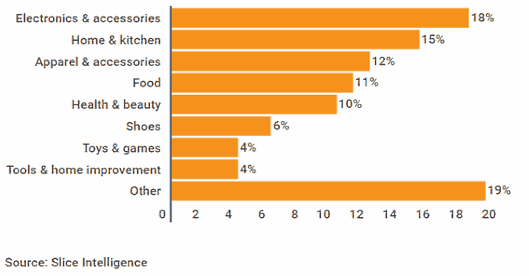検索エンジン最適化(SEO)から検索体験最適化(SXO)への転換を解説するこのコーナー、今回は「レリバンス(Relevance、適合性)」について、説明します。SEOの文脈でコンテンツが語られることも多くなっていますが、レリバンスの観点から、どのようなコンテンツを載せる必要があるのかを説明します。
このコーナーの第1回では、「Search Experience Optimization(SXO)」という考え方と、その3つの構成要素「U・R・A」を解説しました。そして前回の記事では、「U・R・A」の1つ目の要素「ユーザビリティ(Usability)」について説明しました。
今回は、SXOを構成する「U・R・A」の2つ目の要素「レリバンス(Relevance)」です。
「レリバンス」とは、本来「関連性・適切さ・妥当性」といった意味です。検索エンジンマーケティングにおける「レリバンス」とは、次のようなことを指します。
ユーザーの検索行為の持つ「意図」と、検索結果ページの先で出会う「コンテンツ」の「関連性」
つまり、「検索された意図をくみ取り、コンテンツを適合させること=レリバンス」だと言えます。
この記事では、レリバンスという考えの背景や具体的な実施のポイントについて、詳しく説明します。
- 「単語(キーワード)」への適合ではなく、「検索意図(インテント)」への適合という考え方
- レリバンスにおいて重要なポイント(プランニング、コンテンツ、マークアップ)
また、記事の最後には、レリバンス観点を持つべきプレイヤーとコンテンツ制作チームの体制に関しても触れます。
1. 「単語(キーワード)」への適合ではなく、「検索意図(インテント)」への適合という考え方
まず、「SEOにおけるコンテンツの適合性」という言葉を考えた際、みなさんは「何に対して」コンテンツを適合させることをイメージするでしょうか。おそらく多くの方が、何らかの「単語(キーワード)」に対して適合させること、すなわち、ページコンテンツの中に、キーワードを「含有」させ、検索エンジンに対してそのページの内容を伝えることをイメージする方が多いのではないでしょうか。
確かに、従来のSEOでは、キーワードの「含有」がフォーカスされ、「ヘッダーやフッター部分にもキーワードの記述を追加する」「ページ全体に○○%程度キーワードを含むことが好ましい」と言った都市伝説的な手法が重視されていた時代もありました。
こうした小手先のテクニックとも言える施策は、ユーザーに対して向き合うというよりも、検索エンジンが好むポイントや、そのアルゴリズムと向き合うものであり、Googleの進化とともに、その影響度は限りなく弱まっているのが現実です。
Googleは、理念として「Googleが掲げる10の事実」を公表していますが、その最初の項目には、下記のように書かれています。
ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後から付いてくる。
こうした理念に基づき、Googleのアルゴリズムは進化を続けています。特に、2013年9月にGoogleから導入が発表されたコアアルゴリズム「ハミングバード」は、検索クエリ単体でなく、ユーザーの意図に着目するという、「セマンティック検索」をベースに構築されており、検索クエリを通した「意味」を理解することを重視しています。
こうした背景から、Webマスターの方々が向き合うべきは、検索エンジンではなくその先にいる「ユーザー」だと、あらためて認識する必要があります。そして、検索エンジンに対してのみアピールするようなキーワード記述ではなく、「ユーザーが検索行為を通して本当に知りたいこと」、すなわち、検索行為という問いの「意図」に対して、自社のコンテンツを用いて「回答」していくことが求められるのです。これが「レリバンス」の基本姿勢です。
そのため、単語(キーワード)の「含有」という最適化ではなく、キーワードの先にある「検索意図(インテント)」を深く理解し、コンテンツを通して「適合」させていくことが必要とされるのです。
2. レリバンスにおいて重要なポイント(プランニングとコンテンツ制作)
では、具体的にはどのような対応を取ればよいのか。前述のとおり、すべてのコンテンツはキーワードへの適合ではなく、検索意図に対して適合していくことが重要です。具体的には、次の2つが重要です。
- 2-1.検索ユーザーの意図と自社のビジネスゴールを結び付ける「プランニング」
- 2-2.受け皿である「コンテンツ」の制作
それぞれについて、ポイントを解説します。
2-1. 検索ユーザーの意図と自社のビジネスゴールを結び付ける「プランニング」
最初に考えるべきは、「SEOが自社にとってどのような意味を成すか」、つまり「SEOの目的は何か」を明確にすることです。
メディアなど、広告掲載ビジネスモデルの場合、流入数・ページビュー数増加をSEOの目的と考える場合もありますが、多くの事業において、SEO経由での流入を最大化させただけでは、ビジネス上のゴールは達成されないでしょう。
だからこそ、「検索回数の多いキーワードでの上位表示」などをSEOの目的にするのでなく、自社のビジネスゴールを踏まえた上で、SEOの目的は何かということを明確にし、本当に上位表示すべきキーワードなどについて考える必要があります。
その際、いわゆるカスタマージャーニーのような、ユーザーの行動プロセスを細分化し考えることが重要です。ターゲットユーザーをセグメンテーションし、それぞれのフェーズでどのようなゴールを目指すのか、そして、それぞれのフェーズでのゴールを実現するために、どのようなキーワードで検索するユーザーと接点を保つのか、という「キーワードジャーニー」も考えておく必要があるのかと思います。
そして、基軸となるキーワードをもとに、それらのキーワードの背後にあるユーザーの「意図」をあぶり出しましょう。ユーザーの意図を抽出する際には、下記ツールなどが有効活用できます。
- Googleキーワードプランナー、Googleサジェストキーワード
- 検索結果の上位表示ページ
- Q&Aサイト(Yahoo!知恵袋や教えてgoo!など)やキュレーションメディアで閲覧数の多いトピック
Googleキーワードプランナーや、サジェストキーワードでは、実際にユーザーが検索している関連キーワードやその検索ボリュームなどが把握できます。それらの傾向をグルーピングすることで意図をくみ取ることが可能です。
たとえば、キーワード「フットサル 東京」の例で考えてみます。

こちらの検索クエリの先にいるユーザーの検索「意図」を理解するために、キーワードプランナーに加えて、Googleサジェストキーワードのデータを見てみましょう。その際、ユーザーの意図を把握するためには、キーワードの検索回数だけでなく、キーワードが示す「トピック」に焦点を当てることが重要です。
次の図では、検索キーワードをもとに「この検索キーワードは、どういうことに関して(どういうことを念頭に)検索したのか」を推測した「トピック」を追加しています。

たとえば、「フットサル コート 東京」「フットサル 体育館 東京」は、「場所・コート」というトピックに関する検索だということでまとめられます。
同様に、「フットサル 大会 東京」「東京 フットサル 大会」「フットサル 東京 大会」は、どれも「大会」というトピックに関する検索で、キーワードの順序が違うだけだとわかります。
単に文字列でグルーピングしてしまうと、10種類の検索フレーズがあったらそれぞれが別々の検索意図を持つかのように認識してしまいがちです。しかし、このように「何を考えてその検索をしたのか」「その検索でどのような情報を得ようとしているのか」を考えると、また違った「検索意図」のグループが見えてくるのです。
そして、それらのトピックごとにグルーピングしてみると、トピックを通した意図の大小が見えてきます。

こうして整理してみると、「フットサル 東京」が含まれる検索をするユーザーの意図は多岐におよぶものの、特に、個人でフットサルに参加できる「個人参加」について調べている検索が多いことに気付くでしょう。
また、検索意図を探る方法として、検索ボリュームから見ていくのではなく、検索結果の上位表示ページから探るという方法もあります。具体的には、検索結果で上位に表示されているページがどんなトピックを扱っているのかを、各ページのコンテンツから探るのです。
検索結果の上位ページは、「ユーザーの意図を満たしているとグーグルが判断したページ」が表示されているはずです。ですので、上位表示ページに掲載されている「トピック」から、検索エンジンの考える「検索意図」が推測できます。特定のキーワードで検索したときに、1ページ目に掲載されている上位10ページを見れば、傾向がつかめるかもしれません。
さらに、Q&Aサイトやキュレーションメディアを使えば、生の声を通じたユーザーの「知りたいこと」の背景が見えてきます。
そうしたサイトでは、実際のユーザーが「自分の知りたいこと」を投稿しています。そして、その「知りたいこと」に興味がある人が多ければ多いほど、その投稿は人気になります。ですから、閲覧数の多いトピックや人気の投稿などを通して、ユーザーのニーズが推測できるでしょう。
このようにして「ユーザーは何を知りたがっているのか・不安に思っているのか・望んでいるのか・いやがっているのか」というユーザー理解を培い、それをもとに検索意図を把握するのです。
そのうえで、自社が提供できる価値と、ターゲットユーザーが持つ意図の「接点」となるコンテンツやキーワードをプランニングすることを意識しましょう。
2-2. 受け皿である「コンテンツ」の制作
つかまえるべき検索意図を把握したら、次は、実際の受け皿であるコンテンツ制作です。
その際に、考慮しておきたい非常に大切なことがあります。次のことです。
「コンテンツ」は、ユーザーが自分の悩み(欲求・願望・不安・不満などでも可)を解決するための「ツール」となるべし。
われわれは、検索エンジンで何かを検索するユーザーに対して、良い体験を提供しようとしています。
しかし、そもそもユーザーは「検索をしたい」わけではありません。そうではなく、何かしらの悩みや情報ニーズを抱えており、それらを解決したり満たしたりするための「手段」として検索しているだけです。
彼らが本当に求めているのは、「検索結果として出会ったコンテンツを通し、悩みやニーズを満たすこと」なのです。
では、コンテンツがユーザーの悩みやニーズなどに応える「有益なツール」になるためには、何が大切なのでしょうか。
それには、2つの条件があります。
- 2-2-1.内容が優れていること
- 2-2-2.使いやすいこと
コンテンツ制作のポイント1
2-2-1. 内容が優れていること
「内容が優れている」状態というのは、検索意図に答えるために、「網羅性」「専門性」「独自性」の3つを満たしていることが必要だと、私は考えます。
ユーザーの検索クエリの背後にはそれぞれの意図が存在しますが、この意図は非常に多岐にわたります。同じクエリであっても、厳密にはユーザーごとに意図は異なる可能性もあるでしょう。
だからこそ、受け皿となるコンテンツは、その多岐にわたるニーズに対して、「網羅性」を保つ必要があります。そして、ユーザーの抱える悩みを即時に解決できるほどの「専門性」を併せ持つことも求められます。あなたのコンテンツでユーザーが満足し、他のウェブサイトに行くまでもなく、悩みを解決できる状態を目指すことが重要なのです。
さらに、「網羅性」と「専門性」の両方を持つコンテンツに、他のコンテンツにはない「独自性」を持たせなければ、検索エンジンはそのページを評価してくれません。コンテンツに「独自性」を持たせるには、「Webコンテンツに限らず、自社のアセットを広く見てみること」をおすすめします。社内にある既存の資産を使うことで、Webコンテンツに「独自性」を持たせられるケースが多くあるのです。
たとえば、次のようなコンテンツが社内にないでしょうか。
- 定期発行しているカタログ内のコンテンツ
- 実店舗のスタッフが取ったアンケート・お客様の声
- テレビCMなどの動画コンテンツ
こうした自社の保有資産をフル活用することで、ユーザーにとって価値があり、独自性のあるWebコンテンツを作っていきましょう。
コンテンツ制作のポイント2
2-2-2. 使いやすいこと
「内容が優れた」コンテンツを作ると同時に、コンテンツの「使いやすさ」も追求する必要があります。
「使いやすさ」の指標はいくつかあります。いわゆる一般的なWebユーザビリティは当然意識すべきこととして存在しますが、それ以外にも注意すべき点として、次の3点があります。
- 安全性
- 速度
- 読みやすさ
まず「安全性」です。コンテンツがユーザーにとってツールである以上、「安全性」は確実に重要な項目です。
Googleは2014年8月に公式ブログ内で「HTTPSをランキングシグナルに使用する」と発表しています。さらに、ブラウザーのベンダーも、常時HTTPSを標準にしていこうという動きを始めています。
そうした流れを考慮すると、ユーザーがWebサイトを安心して閲覧できる状態を目指すことは、Web担当者にとっても今後さらに重要になってくると考えておくべきでしょう。
「速度」に関しては、モバイルユーザーが増加する昨今、コンテンツをストレスなく閲覧できることは、(前回記事でも説明したように)非常に重要度が高まっているといえるでしょう。
「読みやすさ」に関しては、ユーザー行動の変化に合わせて、Webコンテンツの「フォーマット」も変化する必要があると考えます。
とりわけ、モバイルユーザーの増加と比例し、移動中の閲覧やTVを見ながらの「ながら視聴」も増加し、結果としてコンテンツを「流し読み」するユーザーが増加すると考えるべきでしょう。そうしたモバイルユーザーの行動を意識したうえでのコンテンツフォーマットの変化が重要になると考えます。
具体的には、どういうことでしょうか。すぐに思いつくものとして、たとえば次のようなものがあります。
難しい概念の説明などは、長々としたテキストコンテンツよりも、動画を用いて説明したほうが、ユーザーにとっては理解を深めやすい場合もあるでしょう
モバイルにおいてコンテンツを縦スクロールする前に、目次なりサマリーで内容をまとめておくと親切でしょう
「網羅性×専門性×独自性」を追求した結果としてコンテンツが長文化してしまうときには、画像を効果的に使用することで、ユーザーの閲覧ストレスを軽減し、結果的にコンテンツの滞在時間が長くなったり、読了率が向上したりするかもしれません
こうした仮説を考えるには、ユーザー行動を観察することで、「何がユーザーにとって使いづらいのか」「ユーザーは何がわからなくて困っているのか」「何がユーザーにイヤな思いをさせるのか」を見つけていくのが大切です。
以上のように、コンテンツはユーザーにとって、悩みを解決するための「ツール」であるということを理解し、その意図に答えるために、「網羅性×専門性×独自性」を満たすコンテンツを作り、「内容が優れている」状態を作り出すことが重要です。
そして、「安全性」「速度」「読みやすさ」など、ユーザーにとって自社のコンテンツが「使いやすい」という体験も併せて提供することが、受け皿ページとしてのコンテンツに求められる条件であるといえます。
さら「使いやすいこと」に加えて言えば、人間だけでなく、検索エンジンにとっても「使いやすいこと」は重要です。
前回の記事で解説したように、検索エンジンにとっての「ユーザビリティ」を考え、検索エンジンがページの内容を理解しやすい「マークアップ」を行うように心がけましょう。
レリバンス観点を持つべきプレイヤーとコンテンツ制作チームの体制
最後に、レリバンス観点を持っておくべきプレイヤーとコンテンツ制作チームの体制についても、ポイントを解説しておきましょう。
コンテンツ制作に関してレリバンス観点を持つべきプレイヤーとしては、下記のような立場があります。
- コンテンツストラテジスト
- コンテンツディレクター、コンテンツライター
- マーケッター
前述のとおり、コンテンツ戦略を考える上では、コンテンツにおける「独自性」、つまり、自社の強みやブランドなどを活かしどのようなコンテンツをユーザーに届けるかを、全員がそれぞれの立場で考える必要があります。
まず、「コンテンツストラテジスト」は、コンテンツ全体の戦略立案を行う役割です。自社のコンテンツのミッションや倫理観やモラルを保ちつづけるリーダーシップを発揮し、自社の強みを活かしたテーマの設定、コンテンツの全体戦略立案を行い、それらを実現するコンテンツカレンダーをロードマップとして作成する必要があるでしょう。
そして、そのコンテンツを形にする上で、「コンテンツディレクター」や「ライター」は、コンテンツストラテジストが明確にした自社の強み理解はもちろん、検索結果上の競合コンテンツに対する深い洞察が求められ、ユーザーのインテントに答えるコンテンツを作ることが求められます。
また、「マーケッター」はWebでの広告戦略はもちろん、リアルでの広告戦略とのメッセージの一貫性・整合性を意識することで、コンテンツの価値を最大化し、優れたユーザー体験に対して寄与できるでしょう。
レリバンスを重視したコンテンツ制作においては、本来、訪れた後のユーザーの反応やそれによる影響も含めて、コンテンツを通してユーザーをフォローアップすることが重要です。だからこそ、「コンテンツを公開する」ことだけを目的とした仕組みだけでなく、ユーザーを第一に考え、情報発信者としての志や技術を維持できる仕組みを構築するべきです。
今回は、SXOの中心であり、Webサイトの価値となるレリバンスについてご説明させていただきました。次回は、オーソリティ(Authority、権威性)について解説します。
※このコンテンツはWebサイト「Web担当者Forum - 企業ホームページとネットマーケティングの実践情報サイト - SEO/SEM アクセス解析 CMS ユーザビリティなど」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。
オリジナル記事:SXOで重要な2つ目の要素「レリバンス」――検索意図にコンテンツを適合させる意義と手法 | 時代は「SEO」から「SXO」へ ~海外最新サーチ事情・市場予測
Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.


















![図2:[ユーザー]>[概要(旧サマリー)]レポート](http://web-tan.forum.impressrd.jp/sites/default/files/images/article2016/ga-nyumon/ga-nyumon_201702_02m.png)













![図16:[行動]>[ページ解析]は消滅した](http://web-tan.forum.impressrd.jp/sites/default/files/images/article2016/ga-nyumon/ga-nyumon_201702_11.png)
![図17:[行動]>[サイト コンテンツ]>[すべてのページ]レポートにあった[ページ解析]タブもなくなった](http://web-tan.forum.impressrd.jp/sites/default/files/images/article2016/ga-nyumon/ga-nyumon_201702_12m.png)

![図19:[コンバージョン]セクションのレポート群](http://web-tan.forum.impressrd.jp/sites/default/files/images/article2016/ga-nyumon/ga-nyumon_201702_13.png)