スマホ重視や評価アルゴリズム変更など、2016年も話題に事欠かないSEO(検索エンジン最適化)界隈だったが、2017年のSEOはどうなるのか。
特にECサイトにおけるSEOのポイントについて、楽天株式会社で「楽天市場」のSEOチームでマネージャーを務める近谷康氏と、株式会社アイレップでSEOの責任者を務める吉野五十也氏に、「勝てるECサイトのためのSEO」をテーマに対談してもらった。
「ベーシックなことをやりきる」「ROIで判断する」「時代の変化に対応する」の3つのポイントを挙げた近谷氏がいま一番重要だというのは、やはり「スマホ優先」だ。
2017年のECサイトにおけるSEOのポイント
![]()
吉野 五十也 氏
株式会社アイレップ
執行役員
吉野五十也氏(以下、吉野) まず、お互い簡単に自己紹介しましょう。アイレップは広告代理店ですが、日々の業務では広告を扱わず一貫してクライアントウェブサイトの改善に携わってきた経歴を持っています。
おもに、SEOとコンテンツの領域の責任者をしていて、クライアントのサイトの自然検索をいかに伸ばすかという部分をお手伝いしています。
近谷康氏(以下、近谷) 私は楽天でSEOチームのマネージャーをしていて、チームには数名のSEOコンサルタントがいます。楽天市場はモール型ECモデルで、SEOチームが担当するのはモールの部分です。
私自身は、システム開発の会社でSEをやったあと、楽天に入社してポータルサイトのインフォシークでサービスプロデューサーを担当しSEOを経験しました。2年半くらいたったころでSEOを極めようとアイレップに転職し、2010年からふたたび楽天に戻って現在の仕事をしています。
![]()
近谷 康 氏
楽天株式会社
楽天市場事業 マーケティング部
サーチエンジンマーケティンググループ
マネージャー
吉野 お互いにSEOの経験は10年以上ですが、2017年のSEOで大切なポイントは何だと考えていますか。
近谷 それを解説する前にまず、SEOの根本の部分についてお話しさせてください。
「楽天市場のSEO(検索エンジン最適化)」というとすごいノウハウやテクニックがあるんじゃないかと思われるかもしれません。でも実際には「スペシャルなことは何もしていない」というのが、一番伝えたいことかもしれません。
「何か裏技を知っているんですよね」とか「奇策があるんですよね」といわれますが、楽天市場のように大規模なサイトで継続的に成長させていくためには、一過性の効果しかない、テクニックに偏ったSEOはやりません。
実は、SEOで本当に大事なのはそういったテクニックではありません。継続的に価値を生み出すSEOに大切なことは、
- 奇策ではなく、ベーシックなことをきちんとやりきる
- SEOは売上を上げるためなので、仮説を立て、ROIで優先順位を判断する
- 時代の変化に対応する
この3つくらいでしょうか。
「何か裏技を知らないか?」とか「奇策はないか?」といわれるが、楽天市場のように大規模なサイトで継続的に成長させていくためには、一過性の効果しかない、テクニックに偏ったSEOはやらない。
「スマホ優先」は決定事項なので「対応する」の一択
吉野 「時代の変化」でいうと、最近は何を一番重視していますか?
近谷 いまならスマホ優先ですね。
楽天市場に限らず世のなか全体でPCよりスマホが使われているという流れがあります。グーグルはその流れに対応してスマホページを優先してインデックスし始めます。
だから、スマホ優先やそれに付随したスマホフレンドリーをきちんとやること、それが今の時代で大切なこととして最初に見る点ですね。
この重要性はすでに数字でも出ています。たとえば楽天市場では流通の60%近くがスマホから生まれている状態です。
吉野 アパレルやアクセサリーなど、特定のカテゴリではさらにスマホの比率が高くなりますね。
でも、ウェブ担当者のみなさんは、仕事でデスクトップPCを使っているでしょうから、以外とスマホサイトを見落としがちでは?
近谷 いまは、社内に向けて「PC向けページはスマホ向けページの補完であると考えましょう」というメッセージを出しています。実際に、売上の6割がスマホですし、「PC用のサイトを作ったから、次はスマホ版も作らなきゃ」という時代は終わったといえるのが2017年でしょう。
吉野 世のなか的には、「モバイルファーストインデックス※」を非常に重くとらえている会社が多いようです。
「全部スマホ版で評価されるなら、むしろビジネスチャンスなのではないか。競合より上にいくために何かできませんか」という相談がありました。ただこれは、検索対象がPCからスマホに変わるだけで、スコアリングには影響しないとグーグルはいっています。それでも、「スコアリングに影響するのでは?」「順位が動くのでは?」と懸念される方も多い。
代理店であるわれわれとしては、次の2パターンを用意して選んでいただいています。
- 保守案: PC版の情報をすべてスマホ版に盛り込む(情報を取捨選択して失敗すると怖いので、PC版をそのままスマホ版に)
- スタンダード案:スマートフォンでの情報取得に必要な要素を選定して、十分なコンテンツを入れる
ただ、グーグルとしてはウェブの実態に合わせてくるのが一般的なので、保守案でやると過剰かなというのが正直なところです。
スマホの技術的な面では、「AMP(Accelerated Mobile Pages)」や「PWA(Progressive Web App)」もあります。
AMPは、スマホでのページの表示高速化をめざして複数の企業が参画しているプロジェクトで、グーグルは非常に推しています。PWAは、ウェブでアプリの体験を実現するものですが、こちらは経験のある技術者がまだ少ないので、一般的に認知されるようになるのはまだ先の話でしょう。
近谷 われわれは、スマホを早くから重要視していたという経緯もあって、PC向けとスマホ向けのページは必ず対で存在するということが実現できています。
ですので、「モバイルファーストインデックス」だからとあわてる必要はないですね。
いま課題として残っているのは、「PCはスマホを補完するもの」というように発想を切り替えることですね。以前はその逆だったので、PC向けページに比べて文字や要素を減らしたスマホ向けページもあります。そうしたページはチューニングしていく必要はありますね。
AMPやPWAについては、SEOに直接的な効果があると証明されていない段階なので、選ぶかどうかは各社の判断です。われわれとしては、ページを速く表示する技術としてAMPをとらえた場合、それはユーザーにとって良いことなので、ポジティブにキャッチアップしておくべきと考えています。
仕様も含めてどんどん変化するいまの段階で導入の是非を判断すべきではないし、前もって触れておかないと、仕様が固まったときに初めて取り組んでいるようでは遅いですから。
UX改善はSEOのためでなくユーザーのために
吉野 AMPの話で少し触れましたが、ユーザーエクスペリエンス(以下、UX)についてはどう考えていますか。
近谷 SEOでいう「UX」は、「検索エンジンから来て、モールのなかの店舗で物を買うまで」という外部から内部回遊までの一連の流れ全体を指していると考えています。
一方、社内一般的に「UX」というと、楽天市場トップページからの内部動線に限った話になることが多い印象があります。「トップページを見て、特集を見てから、楽天市場の検索ボックスに何かのワードを入れて検索し、見比べて、アイテムページに行って買う」という、楽天市場内でのメインの動線を改善するという話になるのです。
そういう「理想のサイト内動線」を考えるときは、「まずこのページを見て、次にこれを見てもらう」という流れになっていますよね。でもSEOの場合は、そうした想定ルートと関係なく、グーグルの検索結果から直接店舗さまのページや楽天市場内の検索結果、ランキングのページに行くことがあります。そこが大きな違いで、社内でUXの話をしていると、その話が抜け落ちていることが多いです。
たとえば、トップページからジャンルを絞ってアイテムに行くという流れをスムーズにできるように最適化したとします。そのとおりにユーザーが動いてくれれば非常にわかりやすい導線設計ができあがります。
でもグーグルから来る人は、ジャンルで絞り込んだページに直接、流入することがあります。その人は自分でジャンルを絞った覚えがありません。ですので、そのページではこのページはこういう条件で絞り込んだ内容なのだということが表示されていないと、「何かよくわからないけれど並んでいる」という状態になります。それでは、スムーズに買い物をしてくれるとは限りませんよね。
検索エンジンから訪問するユーザーは前述のような理想の流れを経てそのページを見るのとは前提が違うので、SEOのUXを理解してもらう必要があります。
吉野 なるほど。
近谷 また、SEOでは「クローラビリティ」も無視できません。クローラーも1人のユーザーととらえて、UXの話のなかにクローラーを含んでいるという考え方です。
クローラーも1人のユーザーととらえて、UXの話のなかにクローラーを含めて考える。
吉野 ただ、グーグルのクローラーに対するSEOだけを考えていると、効果がない施策ばかりになってしまうのがいまの時代です。
たとえば、それなりにきちんとナビゲーションが設計されているのに「内部リンクを追加すると良いらしいから」とフッターに無理矢理内部リンクを追加しても、ほぼ意味がないですよね。昔は、そうした行為や、それこそ「タイトルでキーワードをもっと前に置く」といった施策でも結果が出ていました。でもいまは、そうした施策はほぼ意味がありません。だから私は、「ユーザーに向けて、ユーザーに影響がある施策」にと常にいっています。
SEOで行う施策には、「検索エンジン向け」と「ユーザー向け」の2種類あります。もし、読者の方が管理しているサイトで、すでに立ち上げ期を過ぎていてしっかりベースができているのに、やっている施策の8割が検索エンジン向けのものだというならば、内容を見直してみるといいでしょう。フッターやサイドバーにリンクをいくら並べても、ユーザーはそこを見ていません。ユーザーにとって意味のある施策を考えたほうが、結果は出るでしょう。
近谷 そうですよね!
吉野 SEOの世界は変化が激しいのですが、実は2010年前後に大きく変わっています。
以前はテクニカルな要素が強かったんですよ。5年以上前なら外部リンクがすごくSEOに効いていました。また、内部リンクの設計をきちんとやればある程度の結果が出ていました。
しかし、いまは、そうした施策では、ほとんど結果が出なくなってしまっています。もちろん、全然できていないサイトでやれば結果が出るので、「マイナスをゼロにする」という意味では悪くない施策なのですが、100%以上をめざすにはいっさい効かなくなっています。
近谷 グーグルはどんどん進化していますからね。
吉野 それもあるのですが、グーグルが機会学習等の技術を取り入れてきているのが、大きく影響しているのではと私は思います。
グーグルの検索事業の責任者が、アミット・シンハル氏からAI部門の責任者であるジョン・ジャナンドレア氏に変わったことからも、機会学習の活用が進んでいるだろうと推測されます。
つまり、SEOでは4年前の情報、特にテクニックについては効かなくなっていて、以前いわれていたグーグル向け施策は、いまはほとんど効果が出ません。
SEO担当になったばかりの人は、いろいろと調べてそれをやってみようとしますよね。その際に、ネットで検索して見つけたやり方や、制作会社の人が教えてくれたり、セミナーで講師が話していたことを試すこともあるかと思います。
でも、その情報が古いものじゃないかと必ず疑わないとまずい時代になっています。とはいうものの、SEOに詳しくないと、その情報が新しいのか古いのか判断できませんよね。
だから、近谷さんが社内に出すといっていたメールの件と似ていますが、グーグルのためではなくユーザーのためにという考え方で判断するようにしていくのが正しいやり方だと伝えるようにしています。
そもそも、UXをうまく改善できれば、検索トラフィックが増えて、さらに検索以外のチャネルから来た人もスムーズにコンバージョンしてくれるようになるなんて、ROIの観点でもすばらしいじゃないですか!
SEOでは4年前の情報、特にテクニックについては効かなくなっていて、以前いわれていたグーグル向け施策は、いまはほとんど効果が出ない。
近谷 そうですね。われわれもUX専門チームがいるので、A/Bテストをしながらトライ&エラーでいろいろやっています。
社内でも「UXを改善すると検索からのトラフィックが増える」といういい方で推進することはしません。UXはSEO以外のあらゆる成果につながるものですからね。
注意したいのは、「SEOのためにUX改善をする」とは考えないことです。そうではなく、あくまでもユーザーのことを考えて課題であるならUXを改善します。もちろんSEO担当ならば、検索エンジンにも関係するUXはほかの人よりも気にしなければいけませんが。
「SEOのためにUX改善をする」とは考えないこと。あくまでもユーザーのことを考えて、課題であるならUXを改善する。
吉野 スマホのECサイトで他に注意すべき点を紹介するなら、すごく各論になりますが、ページのラベリングを見直したほうがいいというのがありますね。
スマホは画面が狭いので、長い文字列が改行されて見にくいため、省略することが多い。ただし、あまり省略し過ぎるとそれが何のページかわからなくなります。
たとえば、ECサイトのサイト内検索結果ページです。
スマホで見ると、ページに大きく表示しているタイトルが「検索結果」という4文字になっていることが、けっこうあります。4文字ならどんなスマホでも崩れることなく表示できますからね。
でも、検索エンジンからそのページに直接来た人にとって「検索結果」というページタイトルはどうでしょう。何の検索結果かわからないと、ユーザー体験としては良いとはいえませんよね。
だからスマホ向けページでも、「ナイキの検索結果」とか「シルバージュエリーの人気ランキング」とか、最低限の情報は盛り込むべきです。
あとは、細かいことですが、モバイルファーストインデックスのテストと推定される事象も確認されており、PCでグーグル検索したときの検索結果のタイトルに「スマートフォン版」と出て格好悪く見えてしまっていることもあります。
どういうことかというと、スマホ向けサイトのタイトルが「株式会社インプレス 企業概要(スマートフォン版)」のように入れているのが、モバイルファーストインデックスのクローラーの影響でそのまま出てしまっているんですね。
ECサイトのSEOは売上貢献が目的。となると大切なのはROIの意識
吉野 楽天市場のSEOの体制はどうなっていますか。
近谷 ページの仕組みを作っている「開発チーム」と、ページのコンテンツやクリエイティブを作っている「編成チーム」があり、それぞれとSEOの専門家であるSEOチームが一緒にやっていく体制を作っています。
編成チームは、モールでの催し物の場を企画・制作します。季節の特集やジャンルの特集などのページを作って、そこに参加する店舗さまをモール内から募ります。リアルのショッピングモールで広場で催し物を企画してセールをするようなものですね。
たとえば季節の特集では、コンテンツをしっかり作ることが軸になるので、幅広くニーズにあったページをきちんと用意して、それに対して集客していくことが重要になります。どれだけユーザーマッチしたページを用意できるか、ライティングのアドバイスを含めてやっています。
吉野 編成チームが企画したページを作るかどうかは、最終的にSEOチームが決めるのでしょうか。またその場合の判断基準はどのようなものですか。
近谷 われわれは事業としてやっているので、直接的に売上を生むかどうかがページを作成するうえでの基準になります。
一方で、幅広くニーズにマッチしたページを作ることは、購買に直接かかわらない、買うまでに時間のかかるコンテンツを作ることにもなります。購買ファネルでいうとかなり手前の段階なので、われわれの「サイト訪問後24時間でコンバージョンするか」という軸で考えると、なかなか作りにくくて苦労しました。間接的な効果を数字で示しながら、お互いに認識を合わせながら新しいことにチャレンジしています。
われわれは「売り場」「ノウハウ系」「ソーシャルに向き合ったコンテンツ」の3つを、必ず作りましょうという話をしています。特に新しくチャレンジしているのは3つ目のソーシャルの部分で、検索のニーズだけでなくツイッターやはてなブックマークを見て、どういうネタがおもしろいのか話をしながら、編成チームとSEOチーム合同で企画を考えています。
SEOの領域を少し越えますが、そうでないと、おっしゃるとおり差別化できないし、モール型のECは全部一緒という形は避けたいです。
吉野 編成チームとSEOチームの役割分担は、どういうかかわり方をしていますか。
近谷 楽天市場の場合は、企画を考える段階からSEOのコンサルがかかわっています。
たとえば「母の日特集」を作るときに、「母の日」に付随するユーザーのニーズが何なのか、どういうモチベーションの人たちがそこにいるのか、そこからキーワード出しをして、どのようなページをいくつ用意するか決めます。つまり、どのようなページを作るかを決めるためのキーワード出しからやるので、企画が始まる前のキックオフの段階からSEOチームが寄り添って併走する形です。
吉野 SEOチームはキーワードとニーズを出すわけですね。具体的に、どういうものを提供するのですか。
近谷 ぺルソナやシチュエーション、それに対する個々のモチベーションなどからキーワードを類推して、キーワードの検索のボリュームやキーワード同士の関連性を提供します。
キーワードの数でいうと、多分200個くらいは渡しますね。それを「どういう検索モチベーションか」という軸でグループ分けして、サイトマップに落としていきます。
吉野 「母の日」だけや1ワードかけあわせのような単純なキーワードが提供されるわけではないのですね。「このコンテンツは、このキーワードを主軸にこれとこれをこういう構成で入れて」といった指示はしますか。
近谷 コンテンツにキーワードを入れるというより、まずキーワードがあって、そのキーワードのためのコンテンツはこういうテーマだという考え方をします。
「このキーワードで検索された場合にランディングページとなり得るのは、こういうテーマですよ」という形で伝えています。ライティングについては、できあがった文章に対して文字校正をしたり、SEO観点での書き方のチューニングをしたりしています。
編成チームに対するSEOチームのかかわり方
- 「キーワード(ニーズ)A、B、Cを満たすコンテンツとしてページ(テーマ)αを作る」「D、Eを満たすコンテンツとしてページβを作る」という感じで、数十ページ作るようにと編成チームにテーマを提示。
- できあがったコンテンツを文字校正して、検索エンジンが評価しやすいようにチューニング。
どういう切り口のページを作るのかという、粒度とテーマのバランスをとるのが最初の仕事です。
企画によって違いますが、切り口の数は数十、キーワードなら100や200になります。1つの企画につき、数十のコンテンツを作るということです。広く網羅するほど全体のコンテンツの質は上がることになりますが、ページを作るにはコストがかかりますから、そのバランスをとるのが難しい。どのくらい売れるのか予測しながら考えるわけです。
ちなみに、こうした作り方には1つ、意外なメリットがあります。アクセス解析で検索エンジン流入キーワードが見えなくなってしまったという問題がありますよね。でも、この作り方ならばキーワードを前提にテーマを決めてページを作るので、そのページに来たのはそのキーワードからの流入だと見なせるのです。正確ではありませんが、分析には足る情報だと思います。これができるのは、そもそもページを作るときにキーワードありきだからですね。
吉野 では、開発チームに対してSEOチームはどのように取り組んでいるのでしょうか。
近谷 開発に対しては、
- SEO自体の課題抽出をする
- 課題を具体的な施策、たとえば「リンクの張り方を変える」といった施策に落とし込む
- その施策を実施した場合のSEO効果を試算する
- 他の開発案件との優先順位をつけ、優先度が高いものから着手する
という流れです。どれだけSEOチームが「やるべきだ」と思っていても、ビジネスインパクトという観点で他の案件のほうが大きい場合は、そちらを優先します。
吉野 個別の店舗への影響がハードルにはなりませんか? 編成の施策の場合は店舗にとっても嬉しいだけですが、開発の場合は影響が出るケースもあると思います。
近谷 もちろん、各店舗さまのページの基盤となる部分は、非常に慎重に調整しながらやります。ただ、店舗さまのページは店舗さまが自由に編集し工夫されているので、そこに踏み込むことはありません。
吉野 ということは、開発の部分でハードルになるのは、工数とROIがメインということですね。
近谷 ROIですね。
吉野 開発領域のコンテンツには「楽天内の検索結果」と「ランキング」という大切なページがありますが、最近の検索エンジンの傾向として、これらのページに対するトラフィックは変化していませんか?
というのも、楽天に限らずですが、グーグルがコンテンツ感のあるページの順位を上げるしくみになった影響がここに出ている印象があるのです。
昔はグーグルの検索結果で「そのキーワード関連のモール内検索結果ページ」がよく上位にきていたのですが、最近はランキングページの方が上位にくるようになっていますよね。
ビジネス的には、サイト内検索結果ページに入ってきてほしいところでしょうが、どうアジャストしますか。
近谷 SEOの仕事は、すべてのページの順位を上げようとすることです。
もちろん、グーグルのアルゴリズムがどうなっているかは重要な話です。でも、検索上位になってほしくないコンテンツなら消せばいいんですよ。
とはいえ、消すわけにいかないページが検索上位にくることもあります。ですから考え方としては、グーグルは常に変化しているのだから、それに適応するためには、すべてのページが上位になるよう状態にして、アルゴリズムが変化してもいいようにしています。あとは、経営陣も含めて現状と傾向の説明をしっかりすることですね。
もうちょっと現場の話でいえば、上位になっているページがビジネス的に上位にきてほしいページではない場合、「こっちのページをSEOでなんとか上位にする」以外の解決策のほうが現実的なことも結構あります。具体的には、いま検索エンジンで上位にきてるページを工夫して、リンクやバナーをうまく使って露出したいページに誘導すればいいのです。
楽天でいうなら、ランキングのページがグーグルで上位にくるのならば、グーグルで検索したユーザーはそのランキングページに来てもらいます。そこからサイト内検索結果ページへの誘導をしっかりすればいいのです。そのほうが、サイト内検索結果ページがグーグルで上位になるように努力するより自然ですよね。
「カテゴリ」から「タグ」への変更でUXが向上
吉野 楽天市場の開発領域の大きい案件で、「カテゴリ」から「タグ」への移行というリリースが出ています。「タグ化はやりたいけれど、店側に負荷をかけるのでできない」という会社が多いのですが、どのように取り組んだのですか。
近谷 楽天市場というモール全体で考えると、検索して商品にたどり着いてもらうという流れは非常に重要です。しかし、新しい検索体験を提供しようと思っても、いまの検索のしくみのままでは実現できないという課題がありました。そこで手法としてフォーカスが当たったのがタグ化です。
吉野 SEOではなく、UXのためだったということですか。
近谷 そうです。タグ化は、グーグルでの検索順位を上げるためというよりは、UXのために必要な機能としての取り組みです。検索結果ページは、どこから入ろうがみんな通る場所なので、そこを良くしようという話です。
タグ化とはどういうことかというと、たとえば以前の楽天は、ブランド内でカテゴリを横断して探すことができませんでした。
ナイキのスニーカーを探すには「靴」のカテゴリから探します。それは自然です。でも、ナイキには靴以外のファッションもありますよね。しかし以前の楽天市場のサイト内検索では、ナイキのトレーナーを探したければ、「靴」のカテゴリから戻って「ファッション」のカテゴリで検索する必要がありました。ナイキには靴もアパレルもサングラスもスマートウォッチもありますが、それらを「ナイキ」という軸でまとめて探すことができませんでした。
しかし、各商品に「ナイキ」というタグをつけて、タグを軸に検索できるようにしました。これによって、ジャンルを横断した検索ができるようになるのです。
また、タグを使うと、商品に対して簡単に属性を追加でき、意外な絞り込み検索としても使えます。たとえばミネラルウォーターに「500ミリリットル」「36本セット」のような属性をつけられるのです。こうした条件で絞り込むことは、タグ化しなければできませんでした。
これによって「検索から商品へのたどり着きやすさ」が大きく改善しました。
吉野 もちろんカテゴリの仕組みでも要件をつめて開発すればできなくはないけれど、楽天のように大規模だと難しいでしょうから、タグ化はいいしくみだと思います。
近谷 タグ化によっていままでできていなかった機能が実現できると、新しいページが「面」として増えます。このように、機能的に新しいページが増える場合は、必ずSEOチームが入るようにしています。タグ化は、面が増えることでSEOのためにも非常に効果が高い施策になっています。
吉野 タグへの移行はもう完了したのでしょうか。
近谷 しくみとしてはできていますが、データという意味では進行中です。今年いっぱいである程度は完了する予定ですが、楽天は毎日新しい商品が増えるし、属性は常に変化・進化します。
たとえば「以前は業務用で一般の人が使わない物だったのに、突然広く使われるようになった」というように、製造元が意図したのとは違う目的で使うことがブームになることもあります。そういうときにも、新しいタグを柔軟に追加できるのは良いところです。
タグを推進するうえで一番の課題は、各店舗さまがいかに手間をかけずにタグを設定できるかということです。
商品の情報はもっているものの、店舗さまごとで粒度が全然違うので、それをいかに適切に正規化するか、その属性を店舗さま自身で入れられるかというのが、やはり課題です。われわれモールとしては各店舗さまのデータありきなので、いかに入れてもらうかがポイントです。
ECサイトを悩ます「コピーサイト」「詐欺サイト」はどう対応?
吉野 楽天に限らずECサイト全体での困りごとですが、スパムというか、ミラーサイト、詐欺サイトの問題がありますよね。
楽天から情報を全部コピーして、別のサイトに載せているが、実際にそこで買おうとしても商品が届かないというようなサイトです。しかも、ちゃんとサイトを持って運営するのではなく、どこか別のサイトのセキュリティホールをついて、勝手にそのサーバーにコピーしたコンテンツをアップロードしているような……。
もちろんブランドの毀損(きそん)という死活問題もありますが、SEO的には、コンテンツをコピーしているからそのページから楽天に向けたリンクができてしまい、そのリンクが検索エンジンから「よろしくないリンク」だと判断されるリスクがありますよね。
どういう対応を取っていますか。
近谷 われわれはグーグルの検索結果をモニタリングしていますが、見つけた詐欺サイトはすべてグーグルにスパムとして申請しています。かつ、ユーザー向けに楽天市場の詐欺サイト一覧として公開して、注意喚起もしています。
グーグルへ申請をしたら、ハッキングされているサイトだと判定して検索結果に出ないようにしてくれます。
本来グーグルにインデックスされないのが良いですがが、われわれもきちんと監視しています。。
さらに、セキュリティソフトでフィッシングサイトとしてアラートを上げてもらうため、セキュリティベンダーとも連携しているんですよ。
吉野 最後にECのSEOに大切なことは何か、簡単にまとめましょう。
私からは強く伝えたいのは、「人に向けた最適化をしていきましょう」ということですね。
近谷 グーグルの最近の傾向からもわかるとおり「スマホが重要」なので、楽天市場ではスマホの重要度を上げて引き続きやっていきます。あとは冒頭で述べた3つのポイントですね。
- 奇策ではなく、ベーシックなことをきちんとやりきる
- SEOは売上を上げるためなので、仮説を立て、ROIで優先順位を判断する
- 時代の変化に対応する
吉野 ありがとうございました。
近谷 ありがとうございました。
※このコンテンツはWebサイト「Web担当者Forum - 企業ホームページとネットマーケティングの実践情報サイト - SEO/SEM アクセス解析 CMS ユーザビリティなど」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。
オリジナル記事:[対談]2017年のSEOはどうなる? 楽天市場のSEOマネージャー近谷氏とアイレップ吉野氏が語る3つのポイント
Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.
![]()














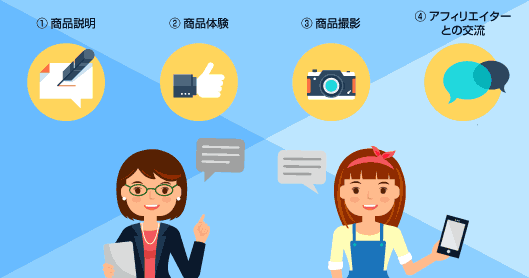























 by
by 









